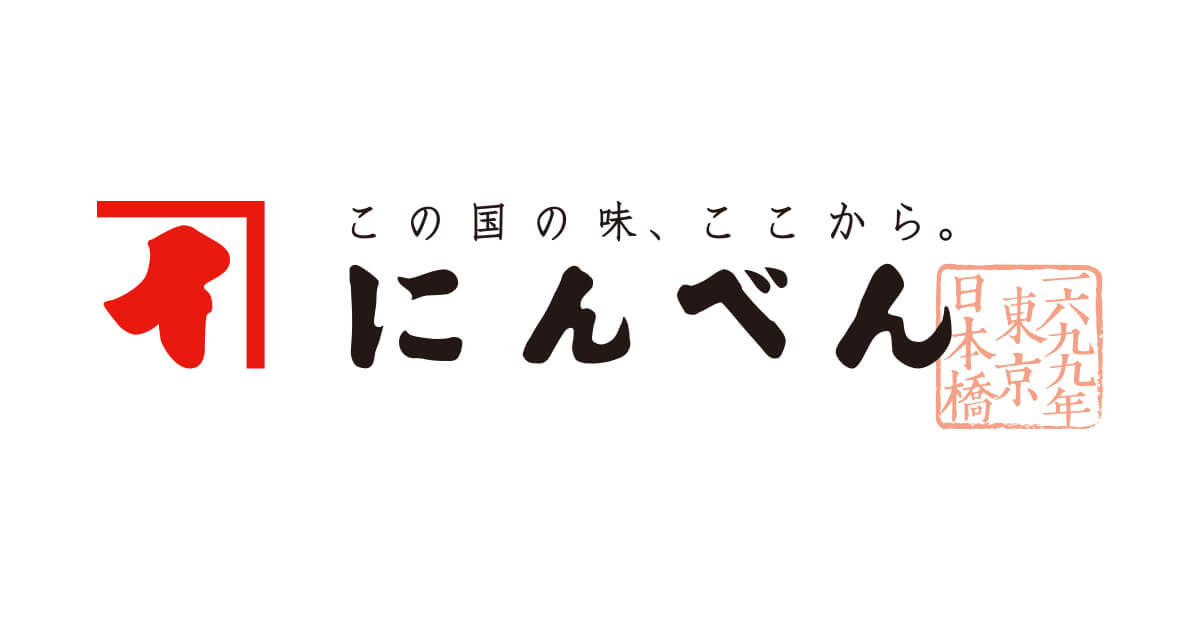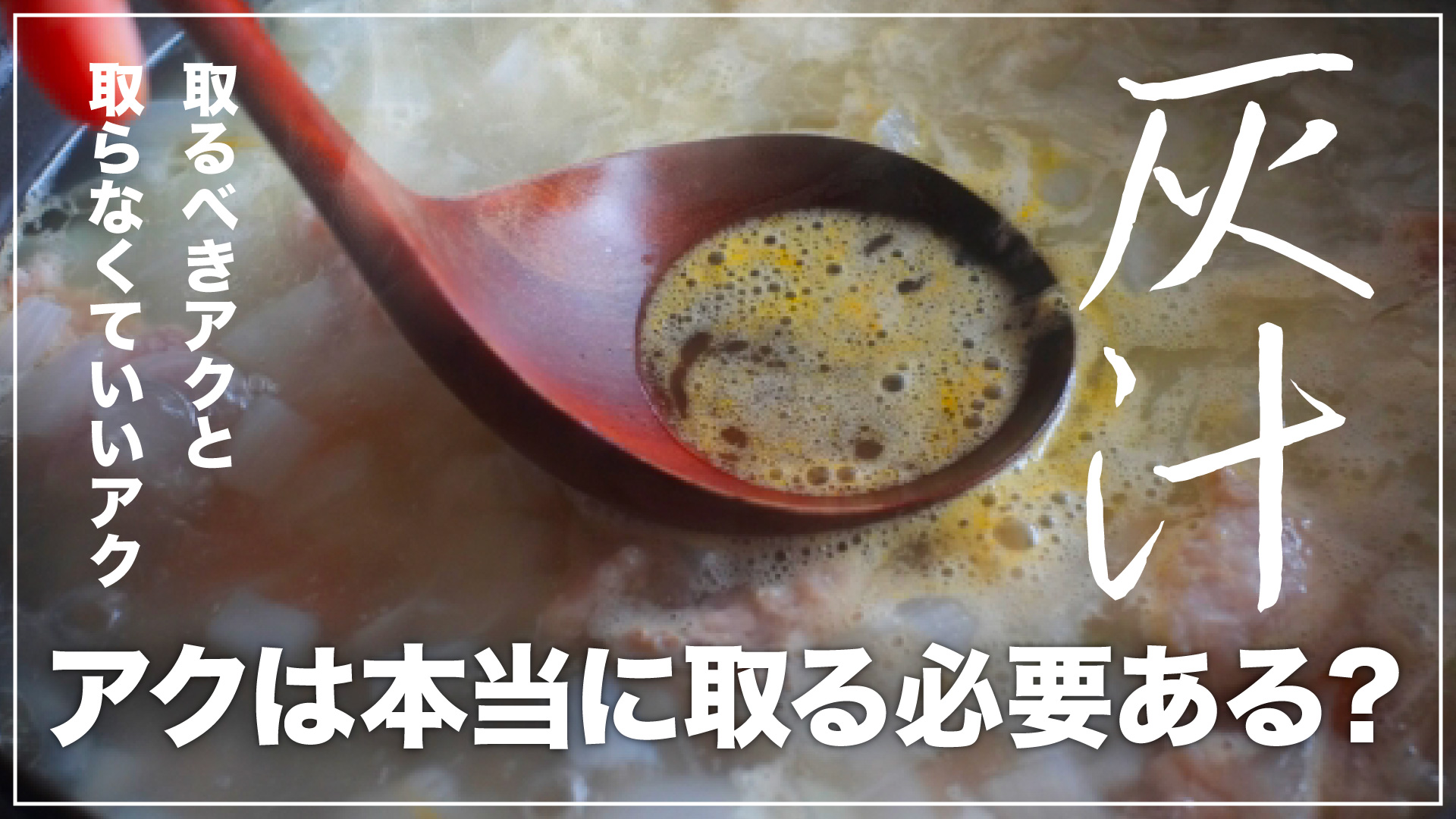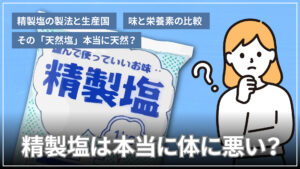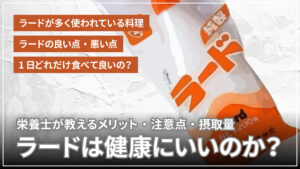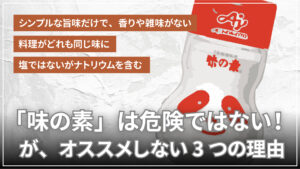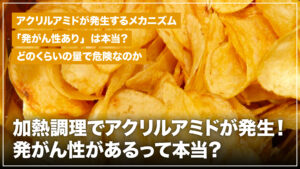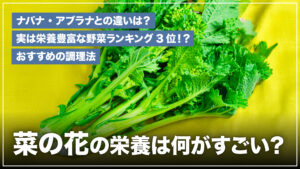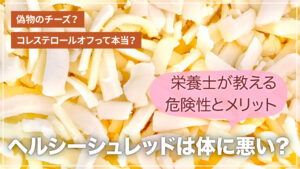煮物やスープを作っていると、白っぽい泡や濁りが出てきます。
私たちはそれを「アク(灰汁)」と呼び、無意識のうちにすくっています。
「でも、そもそもアクって何? すべて取るべき? 実は旨味もあるのでは?」
この記事では、アクの正体を科学的に解説するとともに、そんな疑問を一気に解消します。
アク(灰汁)の正体は何?
アクとは、食品に含まれる渋み・えぐみ・臭みの原因となる成分の総称であり、特定の1つの物質を指す言葉ではありません。
また、煮込み料理で浮いてくる泡だけがアクではないという点も重要です。
動物性・植物性など、食材の種類によってその成分や性質は異なり、対応の仕方も変わってきます。
代表的なアクの種類と特徴
水溶性タンパク質(肉・魚・鰹節)

加熱によってタンパク質が変性し、白〜灰色の泡として浮上したものです。 基本的に食べても問題はありません。
- 特徴: 材料の鮮度が低い場合は臭みの原因になります。
- 対策: 濁りの原因になるので、透き通ったスープ(清湯など)を作りたい時は取り除きましょう。
- 備考: 皆さんが「アク」と聞いてイメージする正体は、主にこれです。
アルカロイド・シュウ酸(山菜・ほうれん草・たけのこなど)

野菜や山菜に含まれる「えぐみ」の主成分です。多量摂取は健康リスク(結石など)もあります。
- 特徴: ゼンマイ、わらび、たけのこなどは苦味が強く、そのままでは食べられません。
- 対策: 必ず「アク抜き(下茹で)」が必要です。これらは煮汁に溶け出す成分のため、浮いた泡を取っても苦味は減りません。材料によってアク抜きの仕方は異なります。
ポリフェノール類(タンニン、クロロゲン酸など)

切った断面が空気に触れて変色(酸化)する原因物質です。
- 対策: 水や酢水にさらすことで変色を防げます。
- 備考: 料理中に浮いてくる「泡のアク」とは異なります。抗酸化作用など健康に有用な成分でもあるため、白く仕上げたい場合以外は、必要以上に気にする必要はありません。
サポニン(豆類・ほうれん草など)

泡立ちの原因となる成分です。 健康への害はありませんが、多いと「雑味」につながる場合があります。
- 特徴: 小豆などを煮るとき、丁寧にアクを取ることで仕上がりがすっきりします。
- 筆者の体験談: 私は自家製あんこを作りますが、実はアクを取った時と取らない時とで、そこまで大きな味の差は感じられませんでした……。
- 余談: ちなみに、フランス料理の「泡のソース(エスプーマ)」などには、このサポニンやレシチンを添加して泡立ちを良くしているものもあります。
結局アクは取った方がいいの?
「アク(灰汁)」という言葉が非常に広い意味で使われていることが、混乱の元になっています。
多くの人がイメージするのは「煮込み料理で浮いてくる泡」ですが、本来、料理の味を損なうため“取るべきアク”とは、山菜や野菜に含まれる「えぐみ成分(シュウ酸など)」のことです。 そして重要なのが、このえぐみ成分は泡状になって浮いてくるわけではないという点です。
したがって私は「浮いてくるアク(泡)を取る必要性はない」という立場です。
アク(泡)を取る必要があるのは以下の通りです。
・透き通った出汁、スープを作りたい(濁りの原因になるため)
・加えた魚、肉の鮮度がイマイチで臭みがある時
・なんか気になる
「アク(泡)と一緒に他の不要な成分も除けるから取った方がいい」という意見もあります。しかし、水溶性の成分であればすでに煮汁全体に溶けているため、表面の泡だけをすくっても味への影響は限定的だと感じています。
ただし、浮いている余分な油脂は取った方がいいでしょう。カロリーオフになりますし、酸化した油脂の臭みも取れます。「脂を取るついでにアク(泡)も取る」くらいの感覚で十分です。
アク取りはプロの現場ではどうなの
「取らなくていい」と言いつつ矛盾するようですが、プロの料理現場ではアク(泡)を丁寧に取ることが一般的です。 それは「見た目」と「洗練された味わい」を重視しているからです。
商品として提供する以上、濁りのない美しい仕上がりが求められます。 また、骨や内臓を使ったスープなどでは、微細な血液由来の成分や臭みが泡に吸着されることもあるため、丁寧にアクを取り除くことで風味がクリアになります。家庭料理とプロの料理では、求めるゴールが違うのです。
必ずアクを取るべき(処理すべき)食材
先ほど「泡状のアクは取らなくてもいい」と述べましたが、えぐみの原因となる植物性のアク(アルカロイドやシュウ酸)については、しっかり処理する必要があります。
特に注意が必要な「シュウ酸」

身近な例としては、ほうれん草に含まれるシュウ酸があります。 シュウ酸は体内でカルシウムと結合し、尿路結石のリスクを高めることが知られています。
最近では電子レンジ加熱による簡単レシピも見かけますが、レンジ加熱だけではシュウ酸が外に溶け出しにくく、残ったままになってしまうことが多いです。健康のためには、たっぷりのお湯で下茹でをして、水にさらしてから使用するのがおすすめです。
まとめ:アクは2種類ある
ここまでの内容を整理します。
- 泡状のアク(タンパク質やサポニン由来):
- 必ずしも取る必要はない。見た目や臭みが気になる時だけ取ればOK。
- 成分としてのアク(アルカロイド・シュウ酸など):
- えぐみや健康リスクの原因になるため、下茹でなどでしっかり除く必要がある。
この2つが混同された結果、「アク=すべて悪いもの=浮いてきたら取る」という誤解が広がったのだと思います。
また、嫌われがちな「えぐみのアク」も、すべてを取り除くのが正解とは限りません。山菜などは、わずかにえぐみが残る方が“山菜の風味”として美味しく感じられることもあります。
料理における「アク取り」は、「なんとなく」で行うのではなく、目的や食材に応じてコントロールすべき技術です。
次回の煮込み料理では、ぜひこの違いを意識してみてください。それだけで料理のレベルが一段上がるかもしれませんよ。
参考: