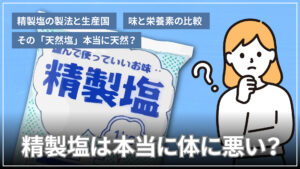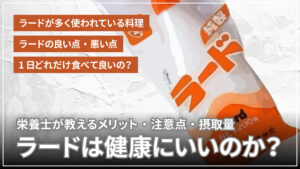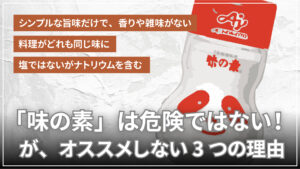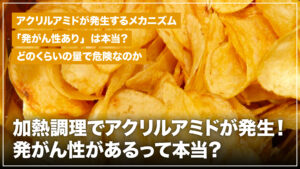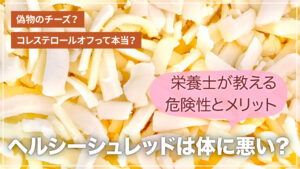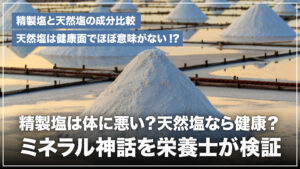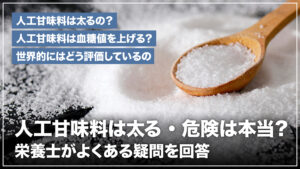「レジスタントスターチ(RS)」という言葉をご存知でしょうか?最近、健康やダイエットの話題でよく耳にするこのワード。 なんと、「ご飯を冷やすだけで太りにくくなる」という夢のような話があるらしいのです。
そんなうまい話が本当にあるのでしょうか?
今回は、レジスタントスターチの仕組みから、どんな食品に多いのか、そして「冷やご飯ダイエット」は本当に効果があるのかまで、栄養士の視点で科学的に解説します。
レジスタントスターチ(RS)とは何か

レジスタントスターチ(Resistant Starch)とは、日本語で「難消化性デンプン」のことです。
デンプンは、消化のスピードによって急速に消化されるRDS(Rapidly digestible starch)、緩やかに消化されるSDS(Slowly digestible starch)、そして難消化性のRS(Resistant starch)の3つに分類されます。
通常、炊いたご飯やパンに含まれるデンプンは、口(唾液)や小腸の消化酵素によって分解され、ブドウ糖として小腸で吸収されます。これが体のエネルギーになりますが、余ると脂肪になったり、血糖値を上げたりします。
しかし、レジスタントスターチは構造が変化しており、消化酵素の攻撃を受け付けません。 そのまま小腸をスルーして大腸まで届きます。
この働きが食物繊維に非常によく似ているため、近年では「第三の食物繊維」や「ハイパー食物繊維」とも呼ばれ、腸内環境改善の切り札として注目されています。
レジスタントスターチ「5つの種類」
RS1:物理的に“消化されにくい”デンプン

構造そのものは普通のデンプンですが、細胞壁・繊維・加工形状によって酵素が届かないため消化されません。
全粒穀物、玄米、未加工の穀物、豆類(硬めのもの)がこれに該当します。粉砕・加熱で消化可能になりやすいため、調理の影響を受けるタイプです。
RS2:消化酵素が入り込みにくい“生のデンプン構造”

デンプン粒の構造自体が強く、酵素が中まで入れないタイプ。高アミロースの「生デンプン」に多い。加熱すると糊化して消化できるようになります。青いバナナ(グリーンバナナ)、生じゃがいも(デンプン粉含む)、ハイアミローストウモロコシ澱粉が該当します。
RS3:加熱後、冷えて“再結晶化”したデンプン(老化デンプン)

今回の記事の主役。
炊いたご飯を冷やした時などに増えるRSがこれです。デンプンが加熱で糊化 → 冷却で再結晶化 → 人の酵素で分解されにくくなるという仕組み。冷やご飯、冷凍おにぎり、冷えたじゃがいも(ポテサラ)などに含まれます。
RS4:化学的に改変された人工デンプン
自然界に存在するものではなく、人の手によって化学的に構造を変えられたデンプンです。
デンプンの分子同士に化学的な「橋」をかけたり(架橋澱粉)、構造を変化させたり(エーテル化、エステル化)することで、消化酵素が入り込めないように頑丈に補強されています。
低糖質食品(低糖質パン、低糖質麺)、特定保健用食品(トクホ)、加工食品全般(食感を良くしたり、とろみを安定させるため)に含まれます。
RS5: アミロースと脂質の複合体
近年、新しく定義され始めた第5のレジスタントスターチ。 デンプン(アミロース)と「脂質(油)」が結合してできるタイプです。デンプンの成分であるアミロースは、らせん状の構造をしています。近くに脂質(脂肪酸)があると、アミロースのらせんの中に脂質が入り込み、強く結びつきます。 この「デンプン+油」の複合体になると構造が安定し、消化酵素が分解しにくくなります。
パン(油脂入り)、クッキー・ビスケット、油を使って炊いたご飯、シチュー・カレールー(小麦粉+油脂)
「ご飯を炊く時にココナッツオイルやオリーブオイルを少し足すとRSが増える」という裏技を聞いたことがあるかもしれませんが、その正体がこのRS5です。 ただし、油を使う分カロリー自体は増えるので、「油を足せば痩せる」と単純には言えない点に注意が必要です。
今回カギとなるのは「RS3」

私たちが日常の食事で意識すべきなのが、このRS3です。 ご飯が冷えてパサパサになったり、少し硬くなったりする現象を「デンプンの老化(レトログラデーション)」と呼びますが、まさにこの状態こそがRS3が増えている証拠なのです。
レジスタントスターチのここがすごい!
レジスタントスターチ(RS)は単に「消化されない」だけではありません。大腸に届いた後、私たちの体に多大なメリットをもたらします。
① 血糖値の急上昇を抑える(セカンドミール効果)
RSは小腸で吸収されにくいため、食後の血糖値スパイク(急上昇)を防ぎます。 さらに面白いのが「セカンドミール効果」です。朝食や昼食でRSを摂ると、その次の食事(セカンドミール)の血糖値上昇まで抑えてくれることが研究で示唆されています。
② 実質カロリーが減る
通常のデンプンは1gあたり約4kcalのエネルギーになりますが、RSは腸内細菌に利用されるため、1gあたり約2kcalとして換算されます。つまり、同じ量のご飯を食べても、RSの割合が多いほど摂取カロリーは低くなります。(出典:消費者庁「食品表示基準」)
③ 最強の腸活成分「酪酸(ラクサン)」を生む
ここが最大のメリットです。RSは大腸で善玉菌のエサとなり発酵しますが、その過程で短鎖脂肪酸、特に「酪酸(ブチレート)」を多く産生します。
【酪酸の働き】
- 大腸のエネルギー源になる: 腸の粘膜を健康に保つ。
- 「痩せホルモン」の分泌: 腸からGLP-1などのホルモン分泌を促し、代謝改善や食欲抑制に働く。
- 免疫の調整・抗炎症: 全身の炎症を抑える効果が期待されている。

実際の冷えたご飯に含まれるRSの量
ご飯を冷やしさえすればレジスタンとスターチが爆上がりして身体にいいんでしょ!?
…と思いきや、実はそうとも限りません。
研究データが示す事実
ある研究によると、ご飯のRS量は以下のように変化すると報告されています。
- 炊きたて: 約8.8%
- 冷蔵(24時間): 約11.7%
- 再加熱: 約9.6%
何と24時間冷やしても3%しか増えません。再加熱すると1%です。一度冷えて結晶化したRS3は熱に強く、電子レンジで再加熱しても「炊きたて」より多い状態を維持します。
冷凍おにぎりはどうなの?
冷凍庫(マイナス温度)よりも、冷蔵庫(4℃付近)の方がデンプンの老化(RS化)は進みやすいと言われています。よって冷凍おにぎりは比較的老化を抑えた処理がされておりRSが低いと予想されます。しかし、冷凍ごはんを解凍する過程でもRSは生成されるため、炊きたてをすぐ食べるよりはRS摂取量は多くなります。
どちらにしろ、劇的に増えるということはなさそうです。
どのくらい「カロリー減」になるの?
ご飯を冷やせばカロリー半分!なんて考えていませんでしたか? そんな甘い話はありません。
実際に計算してみましょう。
茶碗一杯のご飯でシミュレーション
【前提データ】
ご飯の量: 茶碗中盛り 1杯(150g)
デンプンの量: 約55g(ご飯の約60%は水分、残りのほとんどがデンプンです)
通常のデンプン:4kcal/g
レジスタントスターチ(RS):2kcal/g
① 炊きたて55g × 8.8% =RS:約 4.8g
② 冷蔵(24h)55g × 11.7% =RS:約 6.4g
③ 再加熱55g × 9.6% =RS:約 5.3g
【カロリー差の真実】 これらを計算すると、炊きたてのご飯と比べて…
24時間冷蔵したご飯: マイナス 3.2kcal
再加熱したご飯: マイナス 1.0kcal
なんと、ご飯たった2グラム分(数粒程度)の差にしかなりません。 「冷やせばいくら食べても痩せる」というのは大きな誤解です。
結論:冷やご飯ダイエットは成立しない
数字が証明している通り、冷やご飯によるカロリーカットは誤差レベルであり、「冷やご飯を食べれば摂取カロリーが減って痩せる」という考えは、数学的に破綻しています。 「痩せるためだけに冷やご飯を食べる」という努力は、残念ながら徒労に終わる可能性が高いでしょう。
しかし、RSの価値はカロリーではありません。
- 血糖値の上昇が「多少」マシになる
- 食物繊維が「少し」摂れる
- 腸内で「酪酸」という最強の成分を生む
つまり、冷やご飯の正体は「カロリーは変わらないが、食べても太りにくい体質を作るのを助ける、質の良いデンプン」なのです。 多少なりともRSの恩恵にあずかるなら、痩せることではなく、「腸を整えること」を目的にしましょう。
まとめ
この記事で書いたレジスタントスターチ(RS)の真実をまとめます。
| 期待されていたこと | 科学的な真実 | 記事の結論 |
| カロリーが大幅に減る | ご飯1杯で3〜4kcal減の誤差レベル。ダイエットの決め手にはならない。 | カロリー減の期待は厳禁 |
| 食べるだけで痩せる | 減量効果は限定的。代謝(インスリン)改善がメインであり、痩せるには食事量管理が必須。 | 万能食品ではない |
| 腸内環境に効果的 | レジスタントスターチ自体は腸内環境改善に効果的と言える。ただし冷やご飯だけで効果があるかは疑問。 | 多少は効果期待できるか? |
冷やご飯は「魔法の食品」ではない
冷やご飯は、世間で広がるような「食べるだけで痩せる魔法のご飯」ではありませんでした。
しかし、レジスタントスターチ自体の効果は事実です。
レジスタントスターチ単体の研究結果と、ご飯(デンプン)を老化させると一部がレジスタントスターチになる、という事実がごちゃ混ぜになった結果、「ご飯を冷やすと痩せる」というある意味デマ情報になっていったと思われます。
個人的に、レジスタントスターチの効果を期待するならRS3の老化デンプンではなく、雑穀ご飯にしてRS1のレジスタントスターチを狙った方が効果的かと思います。習慣化しやすいですし、何より冷や飯より美味しいです。
また最近ではRS4を使った低糖質パン・麺なども増えてきています。そちらを活用するのも効果的でしょう。
ご飯を冷やすだけで簡単に身体にいいなんて事はありません。
良い栄養士は皆口を揃えて言っています。「バランスよく食べろ」と。それが答えなのです。