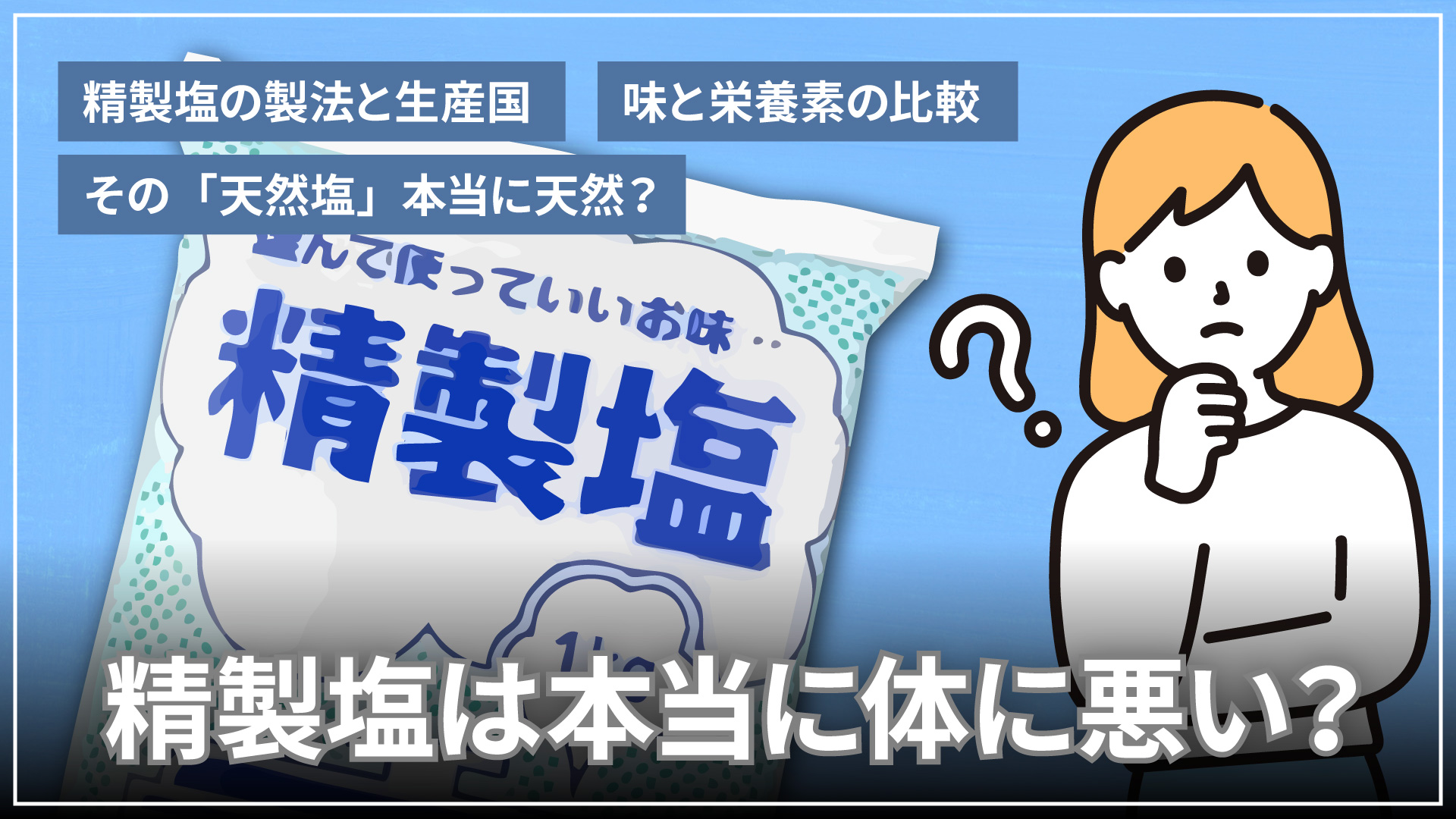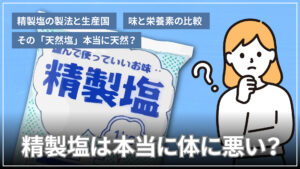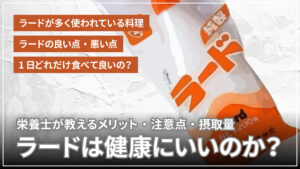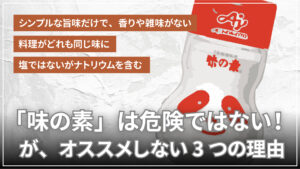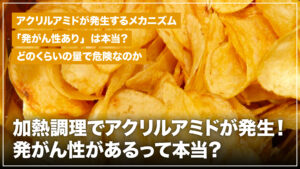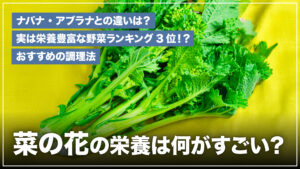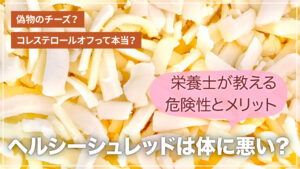塩は、料理に欠かせない調味料のひとつ。
でもスーパーに行くと、「天然塩」「精製塩」「岩塩」「焼き塩」など、似ているようで違う塩がずらりと並んでいて、どれを選べばいいのか迷ったことはありませんか?
とくに
「天然塩は体にやさしい」
「精製塩は添加物で不健康」
「科学的に作られた塩より、自然のものがいい」
といった話を一度は耳にしたことがある人も多いはずです。
では実際のところ、そのイメージは本当なのでしょうか?
この記事では、栄養学と食品表示のルールをもとに、
「天然塩と精製塩は何が違うのか」
「健康面で本当に気にすべきポイントはどこか」
を、栄養士の視点でできるだけわかりやすく整理していきます。
結論:精製塩も元は天然の塩、天然塩のミネラルは微量で意味なし
先に結論だけ書きます。
精製塩も原料は海水由来の天然の塩です。
また、天然塩に含まれるミネラル量はごくわずかで、健康効果を期待できるほどではありません。
このあと本文で、
精製塩・天然塩・再生加工塩の違いを順番に整理していきます。
「結局どの塩を選べばいいのか」
その答えが見えてくるはずです。
「天然塩」の種類と製法
ひとくちに「塩」と言っても、そのルーツはさまざま。
大きく分けると、塩は海塩・湖塩・岩塩の3つに分類されます。
海塩

いわゆる「海の塩」です。
海水を蒸発させて塩を取り出す方法で作られます。
製法には主に2種類あり、
- 太陽の熱で水分を飛ばす「天日塩」
- 火を使って煮詰める「釜焚き塩」
があります。日本で流通している塩の多くが、この海塩にあたります。
湖塩

Image by Leoooooooooo from Pixabay
「塩湖」と呼ばれる、塩分濃度の高い湖から採れる塩です。
水面や地表に塩の結晶が自然に現れるという、特殊な環境で作られます。
死海やカスピ海、アメリカのグレートソルト湖などが有名です。
岩塩

Julia Volkによる写真: https://www.pexels.com/ja-jp/photo/5207320/
太古の海が地殻変動によって閉じ込められ、
数百万年という長い時間をかけてできた塩のかたまりを採掘したものです。

ヒマラヤ岩塩やアンデス岩塩などが有名で、
ピンク色や黒色など、色のついた塩も多く見られます。
世界的には岩塩が主流
世界的な生産量を見ると、
海塩が約3割、湖塩が約1割、岩塩が約6割と、
実は岩塩が最も多く使われています。
国産の塩は海塩
日本では湖塩、岩塩は採れません。なので国産塩は海塩になります。
また、湿度が多いので天日で乾かし切る「天日塩」は少なく、基本的に「釜焚き塩」になります。
精製塩の原料とは

精製塩の原料は、海外から輸入した「原塩」です。
この原塩の多くは、海水を天日で蒸発させて作られた天日塩になります。
意外に思われるかもしれませんが、
精製塩の原料も、もともとは天然の塩です。
では、なぜわざわざ「精製」する必要があるのでしょうか?
原塩はそのまま食べられない
原塩は主に海外の大規模な塩田で作られます。
実際の様子を見ると、広大な塩田で天日干しされた塩を、重機を使って回収しています。

このように作られた原塩は、
砂や小石などの不純物が混ざる可能性があり、
そのままでは日本の食品基準を満たすことができません。
現地である程度の洗浄は行われますが、
それでも国内では食用として販売できない品質です。
なぜわざわざ輸入するのか
日本は塩たっぷりの海に囲まれた国なので、
「わざわざ輸入しなくても作れそう」と思うかもしれません。
問題になるのは、コストです。
海水の塩分濃度はおよそ3%。
つまり、約97%は水分です。
これをすべて蒸発させるには、膨大なエネルギーが必要になります。
さらに、日本は湿度が高く、
海外のように大規模な天日塩田を作るのも難しい環境です。
そのため、
広大な土地と乾燥した気候を活かして、安く大量に原塩を生産できる海外に依存する方が合理的なのです。
調べると東京23区とほぼ同じ大きさの塩田(メキシコ:ゲレロネグロ塩田)に海水を入れて2年かけて蒸発させるとか…規模が違いすぎて、これは輸入したほうがお得だと思いました。「食卓塩」「博多の塩」「シママース」などの原料にもなっています。
原塩を精製したら精製塩
輸入した原塩はいったん国内の工場で水に溶かされ、
濾過やイオン交換膜などの工程を経て、不純物を取り除きます。
こうして純度の高い塩(塩化ナトリウム)だけを取り出し、
安全かつ安定した品質で大量生産したものが精製塩です。
「精製塩は海水を電気分解して作られる」は本当?
この話もよく見かけますが、誤解です。
海水を電気分解すると、
水素・塩素・水酸化ナトリウムが生成されます。2NaCl + 2H2O → 2NaOH + Cl2 + H2
塩なんてできませんね。よって精製塩が、電気分解によって作られているわけではありません。
「イオン交換膜に電流を流し、塩分濃度を高める」という工程はあります。そこを読み間違えたのでしょう。
加えて学生時代の知識と混ざったのでしょうか。あくまでイオン交換膜は濃い海水を作るための装置であって、最終的には熱で乾燥です。
しかし化学的に反応させて塩を作ることはあります。
焼却施設では焼却により発生する塩素ガス(HCl)を、中和させるために苛性ソーダ(NaOH)と反応させます。
そうして安全な塩水(NaCl)として回収します。これを副生塩と言います。
もちろんこのような塩は食用にされることはなく、凍結防止剤や化学工場の原料、皮なめしに使われるそうです。
焼却灰に含まれる塩類は全国で年間18万トンと推定されるそうで、処理が難しく問題になっています。
参考:
リサイクルニュース https://www.trims.co.jp/recyclenews/2013/06/post_1801.html
塩の辞典 橋本壽夫
岩塩や湖塩は精製塩にならないの?
日本では海塩が主流ですが、
岩塩や湖塩も精製塩の原料になります。
外国ではむしろメインです。
いずれも一度水に溶かし、不純物を除去してから塩を作ります。
国によっては、地下から塩水(地下かん水)を汲み上げて製塩するケースもあります。
参考:https://www.shio-ya.com/general_salt/rocksalt.html
精製塩と天然塩、健康への影響は?
純粋な塩化ナトリウム99.5%の精製塩と比べて、天然塩はミネラル豊富で健康に良いと言われています。
果たして本当にそうなのでしょうか?
実際に計算してみると、さほど影響がないことがわかっています。
長くなりましたので別の記事にしてみました。
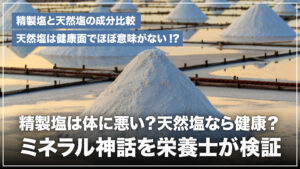
「天然塩」と呼ばれるその塩、実は中身は…?
パッケージや国産表記を見て「天然塩」だと思って買っていた食塩が、
実は思っていたものではないかもしれません。
再生加工塩とは
「再生加工塩」と呼ばれる塩があります。
これは、輸入した原塩をいったん水に溶かし、そこに日本の海水を加えてから、再び結晶化させたものです。
一見すると国産の天然塩に見えても、
原料は海外産の原塩という商品は少なくありません。
「伯方の塩」「沖縄の塩 シママース」「赤穂の天塩」などは、その代表例です。
その土地の海水が混ざっているとはいえ、成分の多くはメキシコやオーストラリアの原塩なのです。
再生加工塩は悪なのか
では、
天然塩のようなパッケージの再生加工塩は「悪い塩」なのでしょうか。
調べていくと、
そこには単なる企業都合ではなく、
日本の塩づくりの歴史や、日本専売公社の横暴、塩田を守ろうとした人たちの事情が深く関わっていることが見えてきます。
結論としては「再生加工塩も選択肢として十分あり」です。
長くなりましたのでこちらの記事で。

そもそも「天然塩」「自然塩」と名乗ってはいけない
ここまで読んで
「今さら?」と思われるかもしれませんが、実は重要なポイントです。
2002年、塩の製造・販売・輸入は原則自由化されました。
しかし当初は表示に関する明確なルールがなく、
誇大な表現やイメージ先行の表示が横行する状態になっていました。
そこで2008年、
食用塩公正取引協議会が発足し、
「食用塩公正競争規約」が制定・施行されます。
この規約は、不正競争防止法や食品表示関連法に基づき、
製法や原料原産地を正しく表示することを目的としたものです。
(参考:食用塩の表示ルール https://www.shionavi.com/salt/display-rules)
表示ルールの主な内容
規約では、次のような表示が制限・禁止されています。
- 「自然」「天然」といった表現の使用
- ミネラルによる優良性を強調する表示
- 「最高」「究極」など、根拠のない最上級表現
- 意味のない「無添加」表示
- 一括表示枠外での、原材料・製法の強調表記
このため現在、
「ミネラル豊富」「自然塩」「天然塩」といった表現は、販売上使用できません。
「天然塩」「自然塩」は、そもそも正式な分類ではない
そもそも「天然塩」「自然塩」という言葉自体、
法律や公的な分類に基づくものではありません。
背景には、1971年に行われた第4次塩業整備があります。
当時の日本では、日本専売公社によって全国26か所の塩田が廃止され、
イオン膜濃縮法を用いた工業的製塩へと集約されました。
(参考:日本専売公社と塩業の歴史
https://www.naikai.co.jp/about/history.html)
このとき、工場で作られる塩は
「化学塩」と呼ばれることもあり、
それに対抗するイメージとして
「天然」「自然」という言葉が広まっていったとされています。
つまり、
「天然塩」「自然塩」は、後から作られたマーケティング用語
という側面が強いのです。
「精製塩には添加物が入っている」は本当?
精製塩は純水は塩化ナトリウムなので、添加物は含まれていません。
そもそも基本的に、塩には保存料は必要ありません。
しかし添加物を加えた塩というものは存在します。
湿度が高い日本ですので、固まるのを防止する目的で入れている添加物がメインになります。
ただ、先ほど紹介した塩の表示ルールの都合上、これらを含まない商品でも「無添加」とは表示できません。
気になる人は成分表を見てチェックするしかありません。
添加物が入っている塩
- 固結防止剤
塩のサラサラ感を保つために使用。日本は湿気が多いため重宝されます。塩を炒ることで、吸湿性の塩化マグネシウムが吸湿性の無い酸化マグネシウムに変化する「焼き塩」も同じ原理です。
「食卓塩」:炭酸マグネシウム
「アルペンザルツ」:炭酸カルシウム
- 風味強化剤
その名の通り風味を強化するために加えます。アミノ酸などが該当します。胡麻、ハーブなどもこの一種ですが、添加物という感じではないですね。
「味の素 アジシオ」:グルタミン酸ナトリウム
「クレイジーソルト」:ハーブ各種
- ミネラル強化剤
主に健康目的でミネラル分を意図的に加えたものです。日本では減塩目的の低ナトリウム塩くらいですが、海外では他にもあります。
「Iodized Salt」:ヨウ素。海のない国でヨウ素摂取のために作られた健康塩。普段海藻を食べてる日本人には不要かつ、ヨウ素添加塩は国内流通禁止。
「フッ素添加食塩」:フッ素。水道水にフッ素を添加し虫歯予防をするのと同じ要領で、水道水の普及していない地域で普及した。日本では禁止。
「減塩タイプのやさしお」:塩化カリウム。ミネラル強化というより、塩のような味の塩化カリウムを添加することで塩(塩化ナトリウム)の量を減らし、それでもしょっぱいという減塩目的。万能ではなく、カリウムも摂取し過ぎると危険。
この塩には添加物が入っていたんだ!と思うでしょうが、
天然塩にはマグネシウム、カリウム、カルシウムなどが豊富です。
精製しすぎた成分を戻しただけ、と言う解釈もできます。
添加物を気にして、買った「天然塩」の方がその成分が多いのです。
味や食感の違い・使い分け方
味の違いについては賛否の分かれるところです。
多くの実験結果では「大きな差はない」と言われていますが、調理の現場においては塩の味の違いは周知の事実とされ、料理によって使い分けられています。
長くなりましたので別の記事にしてみました。他にはない面白い結論だと思いますのでぜひ。

まとめ
「精製塩=化学的なもの」といったイメージ、少しは払拭できたでしょうか?
- 精製塩は海水を天日干しした原塩から精製される
- 天然塩のようなパッケージでも、実は「再生加工塩」のケースが多い
- 天然塩のミネラルは健康に影響を及ぼす量ではない
- 「天然塩」「自然塩」は、後から作られたマーケティング用語
では食塩はどう選んだら良いのでしょうか。
「しお公正マーク」はひとつの判断材料
規約に基づく審査を通過した商品には、
「公正」と記されたしお公正マークが付けられています。

このマークがある商品は、原材料・原料原産地・製法などを、
ルールに沿って表示することが義務付けられています。
塩を選ぶ際の、ひとつの目安として覚えておいてもよいでしょう。
「精製塩は悪、天然塩は善」という単純な話ではありません。
パッケージの印象に惑わされず、原材料や製法に目を向けること。
参考:
食用塩公正取引協議会 – https://www.salt-fair.jp/
公益財団法人塩事業センター「塩百科」- https://www.shiojigyo.com/siohyakka
あらしお株式会社 「精製塩とは?製法から特徴まで、伝統製法の塩との違いも詳しく解説」
https://www.arashio.co.jp/51/