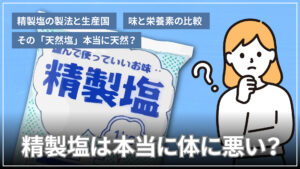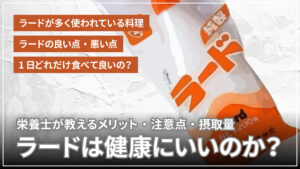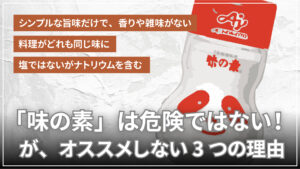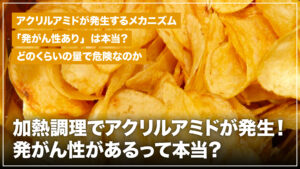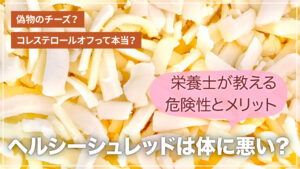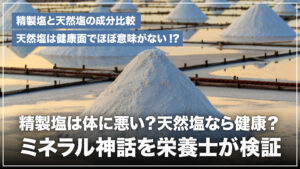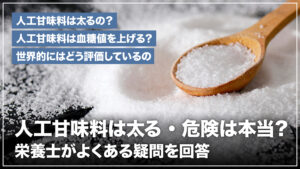「ソーセージやハムなどの加工肉を食べると癌になる」と耳にしたことはないでしょうか。
2015年、世界保健機関(WHO)の国際がん研究機関(IARC)が加工肉を「ヒトに対して発がん性がある」と公式に分類したことから、多くの人の関心を集めました。
しかし「食べたらすぐにがんになる」というわけではありません。
加工肉がなぜリスクとされるのか、そして私たちはどう付き合うべきなのか
栄養士が科学的に解説していきます。
そもそも加工肉って何のこと?

加工肉とは、保存性や風味を高めるために処理された肉製品のことを指します。
代表的なものには以下が含まれます。
- ソーセージ
- ハム
- ベーコン
- サラミ
- コンビーフ など
これらは主に以下のような加工方法で作られています。
- 塩漬け:保存性を高め、独特の風味を付与
- 燻製:香り付けと保存効果
- 発酵:サラミや一部ハムで利用
- 発色剤や保存料の添加:見た目や品質保持のため。風味にも関与
つまり「生肉をそのまま焼いたもの」ではなく、何らかの加工処理を経た肉製品を「加工肉」と呼びます。
国際がん研究機関の評価

2015年、世界保健機関(WHO)の国際がん研究機関(IARC・アイアーク)は、
加工肉を「Group 1(ヒトに対して発がん性あり)」と分類しました。
これは、たばこやアスベストと同じカテゴリーに入ります。
しかし、リスクの強さが同じという意味ではありません。
IARCの結論は、主に大腸がんとの関連を示した大規模な疫学研究に基づいたしっかりとしたものです。
一方で、「どの物質が主な原因か」までは特定されていません。
実際のリスクはどの程度か

IARCが引用したメタ解析によると、
加工肉を1日あたり50g食べ続けると、大腸がんのリスクが約18%増加するとされています。
18%も増加!?大変なことでは??、と思ったそこのあなた。
大丈夫です、実際の数値を出してみましょう。
がんのリスクを数値で見てみよう
この「18%増加」という数字は相対リスクです。単純に18%増加というわけではありません。
絶対リスクに置き換えると、例えば日本人男性の大腸がん発症リスクがおよそ5%とした場合、
5% → 5.9%程度に上がるイメージです。
具体的な数値に置き換えてみましょう。
「通常の食生活の送っている」100人のうち5人が大腸がんになるところ、
「加工肉を毎日50g食べ続けている」100人なら6人が大腸がんになるという計算です。
つまり、「毎日ソーセージやハムを食べ続ける生活習慣」であれば、確かに統計的にリスクは上がります。
そのため、国際がん研究機関(IARC)はヒトに対して発がん性ありと分類したのです。
が、18%の数値そのまま上がるわけではありません。
ましてやたまに食べる程度でがんになるわけではありません。
むしろ、喫煙や過度の飲酒、運動不足など、他の生活習慣要因の方がリスクに大きく影響します。
加工肉の何の成分に発がん性があるのか

先ほども触れたように、「どの成分が主な原因か」までは特定されていません。
ただし加工や調理の過程で発がん性が指摘される物質がいくつか知られており、以下の3つがよく議論されます。
1. 亜硝酸塩とニトロソアミン
ソーセージやハムには、発色剤(亜硝酸ナトリウムなど)が使われています。
これについて「赤く見せて売るためのメーカーの陰謀だ」と言われることもありますが、実際にはもっと重要な目的があります。「赤いだけで売れる」ほど食品開発は甘くないです。
もともとは冷蔵庫のない時代、ボツリヌス菌の繁殖を防ぎ、保存食としての安全性を高めるために使われてきました。
さらに亜硝酸塩を加えることで独特の風味も生まれ、ソーセージやハムの品質に欠かせない要素となっています。
ただ一方で、亜硝酸ナトリウムは肉の成分と反応し、ニトロソアミンという発がん性物質を生成する可能性が指摘されています。また、摂取後にヒトの体内の中でも条件によってはニトロソアミンが生成することが知られています。
とはいえ、食品中から検出される量はごく微量であり、通常の食生活の範囲では健康への影響はほとんど心配ないと考えられています。
2. 多環芳香族炭化水素(PAH)
ベーコンやハムを燻製するとき、煙に含まれる成分から PAH が付着します。
これは焦げや煙由来の発がん性物質で、肉以外の食品(パンや野菜の焦げ)にも含まれることが知られています。
3. ヘテロサイクリックアミン(HCA)
ベーコンやソーセージをフライパンで強火で焼いたり、バーベキューで直火焼きすると、HCAが生成されます。
これも動物実験で発がん性が示されている化合物です。
PAHとHCAについてはこちらの記事でも解説していますが、過度な心配は不要です。
動物実験の結果はあくまで過剰投与だということを念頭においてください。
結論だけ言うと、焦げたステーキ6億枚を毎日食べたら癌になります。そんなレベルです。

加工肉には発がん性を指摘される成分が含まれているのは事実ですが、いずれも微量であり、常習的かつ大量に摂取し続けなければ大きな問題にはならないと考えられます。
加工肉とどう付き合うべきか

加工肉は身近で手軽に使える食材ですが、毎日の習慣にするのは避けた方がよいと国際的に指摘されています。
とはいえ、完全に排除する必要は全くありません。
50g以上日常的に食べている人は、頻度と量を気持ち控える程度で十分だと考えます。
その場合も発がん性物質うんぬんより、動物性脂肪と塩分の心配をした方がいいでしょう。
結局のところ、「毎日大量に食べ続ける習慣」を避け、食事全体のバランスを整えることが一番の対策です。
まとめ
- ソーセージやハムなどの加工肉は、保存や風味を高めるために塩漬け・燻製・添加物などを用いた肉製品。
- WHO/IARCは加工肉を「Group 1(ヒトに発がん性あり)」に分類し、特に大腸がんリスクとの関連を示している。
- ただし、これは「毎日50g以上食べ続けた場合に統計的リスクが上昇する」というもの
- 100人中5人が大腸がんになるところ、100人が加工肉を毎日50g食べ続けると6人くらいになると言う計算。
- 実際のリスクは「食べる量や頻度」「生活習慣全体」に左右される。
参考文献
- World Health Organization (WHO). Cancer: Carcinogenicity of the consumption of red meat and processed meat
https://www.who.int/news-room/questions-and-answers/item/cancer-carcinogenicity-of-the-consumption-of-red-meat-and-processed-meat - 農林水産省. 国際がん研究機関(IARC)による加工肉及びレッドミートの発がん性分類評価について
https://www.maff.go.jp/j/syouan/seisaku/risk_analysis/priority/hazard_chem/meat.html - 国立がん研究センター 社会と健康研究センター. 赤肉・加工肉摂取量と大腸がん罹患リスクについて
https://epi.ncc.go.jp/jphc/outcome/2869.html - CIR(CiNii Research). 食品中のニトロソアミンについて
https://cir.nii.ac.jp/crid/1390001204224714496 - 農林水産省. ニトロソアミン類とは
https://www.maff.go.jp/j/syouan/n_nas/about.html